トリミング・鍼治療・ペットマッサージは完全予約制です!!
必ず前日までに(空き状況の確認が必要のため診察時間内に)ご予約下さい
当院のお休みは木曜・日曜・祝日です。
当院の基本情報に関してはコチラの記事をご覧ください。
鍼治療に関してはコチラの記事をご覧ください。
漢方についてはコチラの記事をご覧ください。
夜間の緊急受診は当院ですぐに対応できないことが多いため、
静岡市夜間救急動物病院への受診をおすすめしています。(年中無休PM9:00~AM1:00)
☎054-269-4199(必ず受診前に☎をして下さいね)
静岡市葵区土太夫町17-1
2019年03月29日
春です!
静岡県では桜の開花宣言もされていよいよ春本番
暖かいのは過ごしやすく嬉しいことですが、暖かくなってくると困ることが・・・
「皮膚のかゆみ」
と
「ノミマダニの寄生」
皮膚のかゆみはノミマダニなどの寄生でもおこりますが、それ以外でも色々な要因でおこります。
また複雑にいくつかの症状が絡み合ったり、治療も長引くまたはずっと治療が必要なわんちゃんも多く、飼い主さんも悩まれていることだと思います。
一般的に暖かい時期や夏はかゆみの症状が強くなることが多いです。
治療方法も様々で、注射・飲み薬・フード・薬用シャンプー・外部寄生虫対策など・・・
また生活環境も大切でお掃除をこまめにする、アレルギーがある場合はそれを極力取り除くなども必要です。
アレルギー検査をおこなうと、わんちゃんでも食物アレルギーがあったり、カビのアレルギー、スギ花粉アレルギーがあることもあります。
わんちゃんのかゆみについて、わかりやすくまとめられているサイトがありますのでご紹介します。
治療についても掲載されています。
お薬メーカー、ゾエティスさんのサイトです→「犬のかゆみ治療.com」
アレルギー検査は検査期間でおこなう検査で、結果まで1週間程度かかりますが、検査自体はいつでもおこなえます。
気になる方はご相談くださいね。
ノミマダニについてですが、今年ももう寄生がチラホラ確認されています。
対策としては、くさむらにはなるべく近づけないこと、お薬で定期的に予防をおこなうことです。
方法は滴下式といわれる首のうしろに液体をつけるタイプと、美味しいお肉に薬を溶かしたお肉のチュアブルタイプです。
市販ですとノミ取り首輪がありますが、ノミ取り首輪を噛んだことによる中毒が起こる場合もあり、皮膚に合わないとかぶれる・脱毛もありますし、注意が必要です。
また市販の滴下式のお薬と病院の滴下式のお薬は成分が異なります。
ノミやマダニはかゆみを引き起こす以外に、様々な病気を媒介することが知られています。
これは人に対しても同様です。
最近ですと、マダニが媒介したSFTSという病気で何例も死亡例が確認されていて大変怖いです。
おうちの中で繁殖してしまうと、一年中悩まされることにもなります。
家に持ち込まないことも大切ですね。
お散歩から帰ってきたら全身チェックもお忘れ無く!
わんちゃん猫ちゃん、そして飼い主さんご自身を守るためにもしっかりしたお薬で予防をおこないましょう!
ノミマダニについてもゾエティスさんのサイトでわかりやすくまとめられていますので、ぜひご一読ください。
↓
「犬のノミ・ダニ.com」
↓ こちらのバナーからも飛べます!
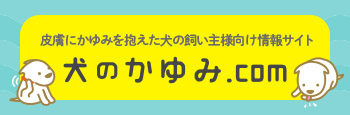
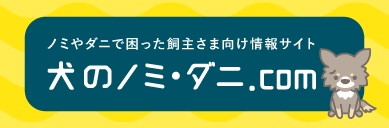

暖かいのは過ごしやすく嬉しいことですが、暖かくなってくると困ることが・・・
「皮膚のかゆみ」
と
「ノミマダニの寄生」
皮膚のかゆみはノミマダニなどの寄生でもおこりますが、それ以外でも色々な要因でおこります。
また複雑にいくつかの症状が絡み合ったり、治療も長引くまたはずっと治療が必要なわんちゃんも多く、飼い主さんも悩まれていることだと思います。
一般的に暖かい時期や夏はかゆみの症状が強くなることが多いです。
治療方法も様々で、注射・飲み薬・フード・薬用シャンプー・外部寄生虫対策など・・・
また生活環境も大切でお掃除をこまめにする、アレルギーがある場合はそれを極力取り除くなども必要です。
アレルギー検査をおこなうと、わんちゃんでも食物アレルギーがあったり、カビのアレルギー、スギ花粉アレルギーがあることもあります。
わんちゃんのかゆみについて、わかりやすくまとめられているサイトがありますのでご紹介します。
治療についても掲載されています。
お薬メーカー、ゾエティスさんのサイトです→「犬のかゆみ治療.com」
アレルギー検査は検査期間でおこなう検査で、結果まで1週間程度かかりますが、検査自体はいつでもおこなえます。
気になる方はご相談くださいね。
ノミマダニについてですが、今年ももう寄生がチラホラ確認されています。
対策としては、くさむらにはなるべく近づけないこと、お薬で定期的に予防をおこなうことです。
方法は滴下式といわれる首のうしろに液体をつけるタイプと、美味しいお肉に薬を溶かしたお肉のチュアブルタイプです。
市販ですとノミ取り首輪がありますが、ノミ取り首輪を噛んだことによる中毒が起こる場合もあり、皮膚に合わないとかぶれる・脱毛もありますし、注意が必要です。
また市販の滴下式のお薬と病院の滴下式のお薬は成分が異なります。
ノミやマダニはかゆみを引き起こす以外に、様々な病気を媒介することが知られています。
これは人に対しても同様です。
最近ですと、マダニが媒介したSFTSという病気で何例も死亡例が確認されていて大変怖いです。
おうちの中で繁殖してしまうと、一年中悩まされることにもなります。
家に持ち込まないことも大切ですね。
お散歩から帰ってきたら全身チェックもお忘れ無く!
わんちゃん猫ちゃん、そして飼い主さんご自身を守るためにもしっかりしたお薬で予防をおこないましょう!
ノミマダニについてもゾエティスさんのサイトでわかりやすくまとめられていますので、ぜひご一読ください。
↓
「犬のノミ・ダニ.com」
↓ こちらのバナーからも飛べます!
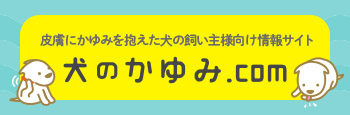
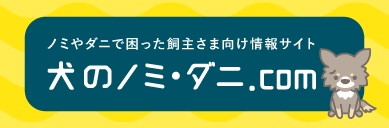
2018年06月04日
みりんちゃんの歯石
当院の看板犬(?)みりんちゃんも御年10歳を超えまして、色々と気になるお年頃になってきました。
歳をとってくると気になるのが歯です。
犬の場合、人間と比べて虫歯になることはまずありません。
その代わり、歯石がとてもつきやすい動物です。
歯石は一度ついてしまったら簡単にとることは出来ません。
そして、歯石はばい菌の塊のようなもの。そこから歯周病が起こり、全身に影響を及ぼすこともある怖い状態です。
またひどいと細菌感染から膿が出てきたり、ほっぺの部分に穴が開いてしまうことも珍しくありません。
口臭もひどくなりますから、においが気になる方もいらっしゃるでしょう。
重度の歯周病の場合、歯の根っこが腐ったようになってしまい、歯石を取ると簡単に抜けてしまうこともあります。
こういう状態になってしまうと、人間と違ってわんちゃんはじっとしてくれませんから、全身麻酔をかけての処置となります。
ここまでいかない状態でも歯科処置に全身麻酔は必須です。
無麻酔での歯石取りはおすすめできません。
歯の表面に傷をつけて余計歯石をつきやすくしてしまったり、わんちゃんが動いたり暴れたりしたら傷つけてしまう恐れもあります。
話を戻してみりんちゃんです。
彼女もすっかりお口に歯石がつきました。
現時点で症状は出ていませんが、今後はわかりませんし、年齢的にもそろそろということで歯石除去処置をおこないました。
こちらが処置前の写真。

処置後の写真。

きれいになりました~
お口の健康を保って、まだまだ長生きしてもらいたいです。
ちなみに、歯石はとっても何もしなければ必ずまたつきます。
今は色々な歯磨き製品やサプリメントが出ています。
何かおうちでやれることを試していけるといいですね。
当院でも待合室や受付で歯磨き関連のグッズをご紹介しています。
使い方のご説明も致しますのでお気軽にご相談くださいね。
歳をとってくると気になるのが歯です。
犬の場合、人間と比べて虫歯になることはまずありません。
その代わり、歯石がとてもつきやすい動物です。
歯石は一度ついてしまったら簡単にとることは出来ません。
そして、歯石はばい菌の塊のようなもの。そこから歯周病が起こり、全身に影響を及ぼすこともある怖い状態です。
またひどいと細菌感染から膿が出てきたり、ほっぺの部分に穴が開いてしまうことも珍しくありません。
口臭もひどくなりますから、においが気になる方もいらっしゃるでしょう。
重度の歯周病の場合、歯の根っこが腐ったようになってしまい、歯石を取ると簡単に抜けてしまうこともあります。
こういう状態になってしまうと、人間と違ってわんちゃんはじっとしてくれませんから、全身麻酔をかけての処置となります。
ここまでいかない状態でも歯科処置に全身麻酔は必須です。
無麻酔での歯石取りはおすすめできません。
歯の表面に傷をつけて余計歯石をつきやすくしてしまったり、わんちゃんが動いたり暴れたりしたら傷つけてしまう恐れもあります。
話を戻してみりんちゃんです。
彼女もすっかりお口に歯石がつきました。
現時点で症状は出ていませんが、今後はわかりませんし、年齢的にもそろそろということで歯石除去処置をおこないました。
こちらが処置前の写真。
処置後の写真。
きれいになりました~

お口の健康を保って、まだまだ長生きしてもらいたいです。
ちなみに、歯石はとっても何もしなければ必ずまたつきます。
今は色々な歯磨き製品やサプリメントが出ています。
何かおうちでやれることを試していけるといいですね。
当院でも待合室や受付で歯磨き関連のグッズをご紹介しています。
使い方のご説明も致しますのでお気軽にご相談くださいね。
2016年12月21日
あごにきび
以前にもブログに書いたのですが、このブログの検索キーワードを調べると必ず上位にいるのが「あごにきび」です。

↑ これ今月の検索キーワード順位です。
上位にあごにきび関連がいっぱいです。
2011年に何気なく書いた記事がきっかけで、わざわざ遠方からお電話で問い合わせをもらったこともあります。
そしてそれ以来上位がずっとあごにきび。
当院があごにきびの専門治療をおこなっているわけではありませんので、あしからず・・・
この反響を受けて、皆さんそれだけあごにきびについて気になっているんだとわかり、私自身も今まで何気なく見ていたものが気になるようになりました。
病院にかかるほどではないんだろうけれど、猫のあごの下にあるこの黒いぶつぶつはなんだろうって思われますよね。
あごの下は猫ちゃん自身が自分できれいに出来ません。
そのため、脂や汚れが毛穴に詰まってしまいます。その正体があごにきびです。
つまりにきびと同じ原理ですね。
これは個体差があって、こうなりやすい子と全然ならない子と色々です。
通常は放っておいて問題ありません。
可能であれば、時々清潔にするために清拭してあげるといいです。
と、ここまでは以前からお伝えしている内容なのですが、あごにきびで病院にかかるレベルの症例がありましたので今回ご紹介します。

↑ 赤くなって炎症をおこしてしまっています。

↑ 治療として毛を刈りました。
写真だとわかりづらいですが、ジュクジュクして化膿してしまっていました。
このあと1日1回、抗生剤のクリームを塗りました。
10日後の写真がこちらです。

↑ 赤みがすっかりなくなり、きれいになりました。
実はこの猫ちゃん、うちの「きび」です。

↑ ボケてしまってますが、よく見るとあごの毛がサッパリしているのがわかるでしょうか。治療中に撮った写真です。
自分のうちの猫があごにきびで病院にかかることになるとは!
私はあごにきびと何か縁があるのかなぁと思いました(笑)
しかも「きびのあごにきび」とはなんだかおもしろい語呂になってしまいました。
このような状態になった場合は、動物病院で受診しましょう。
時々猫ちゃんのあご、チェックしてあげてくださいね!
↑ これ今月の検索キーワード順位です。
上位にあごにきび関連がいっぱいです。
2011年に何気なく書いた記事がきっかけで、わざわざ遠方からお電話で問い合わせをもらったこともあります。
そしてそれ以来上位がずっとあごにきび。
当院があごにきびの専門治療をおこなっているわけではありませんので、あしからず・・・
この反響を受けて、皆さんそれだけあごにきびについて気になっているんだとわかり、私自身も今まで何気なく見ていたものが気になるようになりました。
病院にかかるほどではないんだろうけれど、猫のあごの下にあるこの黒いぶつぶつはなんだろうって思われますよね。
あごの下は猫ちゃん自身が自分できれいに出来ません。
そのため、脂や汚れが毛穴に詰まってしまいます。その正体があごにきびです。
つまりにきびと同じ原理ですね。
これは個体差があって、こうなりやすい子と全然ならない子と色々です。
通常は放っておいて問題ありません。
可能であれば、時々清潔にするために清拭してあげるといいです。
と、ここまでは以前からお伝えしている内容なのですが、あごにきびで病院にかかるレベルの症例がありましたので今回ご紹介します。
↑ 赤くなって炎症をおこしてしまっています。
↑ 治療として毛を刈りました。
写真だとわかりづらいですが、ジュクジュクして化膿してしまっていました。
このあと1日1回、抗生剤のクリームを塗りました。
10日後の写真がこちらです。
↑ 赤みがすっかりなくなり、きれいになりました。
実はこの猫ちゃん、うちの「きび」です。
↑ ボケてしまってますが、よく見るとあごの毛がサッパリしているのがわかるでしょうか。治療中に撮った写真です。
自分のうちの猫があごにきびで病院にかかることになるとは!
私はあごにきびと何か縁があるのかなぁと思いました(笑)
しかも「きびのあごにきび」とはなんだかおもしろい語呂になってしまいました。
このような状態になった場合は、動物病院で受診しましょう。
時々猫ちゃんのあご、チェックしてあげてくださいね!
2016年11月19日
寒くなってきました!
↑ これ、何かわかりますか?
寒くなると増えるのが膀胱炎です。
このブログでも毎年のようにお伝えしていますが、特に怖いのが猫ちゃんの男の子の膀胱炎。
猫の膀胱炎の原因は結晶で起こることが多く、写真はおしっこの中の結晶を顕微鏡で見たものでした。
この結晶が細くて長い尿道を詰まらせてしまうことがあります。
そうなるとおしっこが出せなくなり、急性腎不全をおこし最悪死に至る怖い状態(尿道閉塞)となります。
猫ちゃんの男の子で何度もトイレに行くような症状が見られたら要注意!
早めに動物病院を診察しましょう。
そのうち治るでしょと様子を見ると大変なことになる場合があります。
明らかにおしっこが出ていないときは緊急で診察が必要です。
冒頭の写真の猫ちゃんは夜間で緊急来院されました。
無事開放に向かい一安心したところです。
寒くなったんだなぁと思いました。(とはいえ真夏でもおこる場合はあります)
膀胱炎の主な症状:トイレに何度もいく・トイレでずっとしゃがんでいる・トイレ以外で粗相をしてしまう・おしっこに血が混じっている・おなかが膨れてくる・元気食欲がなくなる・何度も吐くなど
ちなみにまれですが、女の子でも尿道閉塞を起こすケースもありますので、女の子であってもおしっこが出ているかどうかは常日頃から十分観察してください。
おしっこは腎臓病になりやすい猫ちゃんにとって、病気の大切なサインです。
量がいつもより多い・少ない・においがおかしい・色がおかしい・・・などいつもと違う状態は要注意です。
おしっこが採れるようでしたら、ぜひ定期的な検尿をおすすめします。
一番怖いのは外でおしっこをしてくる猫ちゃん。
外だと出ているのかおかしいのかチェックが難しくなってしまいます。
外に出る猫ちゃんで発見が遅くなり、残念ながら命を落とすケースもあります。
他人のおうちで粗相をすれば当然トラブルにもなりますので、こうした観点からも猫ちゃんは完全室内飼いが望ましいですね。
2016年10月22日
乳歯遺残
きびちゃんの犬歯、乳歯が残ったまま永久歯が生えていることが発覚しました。
この写真でわかりますでしょうか?
下にある人の親指があたっているところです。
上顎も下顎も残っています

わんちゃん猫ちゃんも歯の生え変わりがあり、乳歯から永久歯になります。
まず乳歯は生後1か月ほどで生え始めます。
永久歯に生え変わる時期は、生後4~5カ月くらい。
この歯が生える時期は甘噛みがひどく、飼い主さんも苦労される場合がありますね。
大抵は知らない間に生え変わっています。
落ちている乳歯を見つけたらラッキーです。

↑ これはうちのボーダーコリーみりんちゃんの乳歯です。
抜けるときはこのように根元の方(写真でいうと上側)が溶けたようになって抜け落ちます。
乳歯は自然と生え変わる場合もありますが、抜けずに残ってしまい、そのまま永久歯が生えることがあります。
これを乳歯遺残(にゅうしいざん)といいます。
大抵は知らない間に生え変わっています。
落ちている乳歯を見つけたらラッキーです。
↑ これはうちのボーダーコリーみりんちゃんの乳歯です。
抜けるときはこのように根元の方(写真でいうと上側)が溶けたようになって抜け落ちます。
乳歯は自然と生え変わる場合もありますが、抜けずに残ってしまい、そのまま永久歯が生えることがあります。
これを乳歯遺残(にゅうしいざん)といいます。
残ってしまった乳歯はその後抜けることがほぼありません。
しかしそのまま放っておくと歯と歯の重なり部分に歯石がたまったり、歯並びに影響が出たりします。
動物はじっとしてくれませんし、根っこが残った乳歯を抜くのはとても痛いですので、鎮静をかけて抜歯をおこないます。
多くの飼い主さんは避妊や去勢手術をおこなう際に、一緒に抜く方が多いです。
↑ これが抜けなかった乳歯を抜歯したものです。
写真の向きが逆でしたが、こちらは下側が根っこ部分です。
しっかり根っこが残っていますね。
抜けにくい犬種というのがありまして、小型犬は残りやすいです。
特にトイプードル、ミニチュアダックス、チワワ。
多い子だと8本抜く子もいます。乳歯だけでなく臼歯が残っている場合もあります。
猫は通常残ることはほとんどないのですが、まさかきびちゃん残ってしまうとは・・・
去勢手術の時に一緒に抜いてもらおうと思います。
2015年12月26日
おしっこ出ていますか?

今週は猫ちゃんのおしっこの病気がとても多かったです。
膀胱炎ならまだよいのですが、怖いのが尿道が詰まっておしっこが出なくなってしまう状態です。
この場合は緊急で処置が必要です。
おしっこは本来外へ出なければならないもの。
これが何らかの原因で(猫の場合は結晶のせいであることがほとんどです)外に出せなくなると、膀胱だけでなく腎臓にもダメージがいきます。
そのまま数日放置しておけば死に至る大変怖い状態です。
猫が何度もトイレに行っている場合は、おしっこが出ているのかどうか観察することがとても大切です。
特にオス猫の場合は、尿道が長く細いためメスに比べ詰まりやすいです。
オス猫で去勢手術済、さらに太っている場合はリスクがかなり高くなります。
おしっこが出ているようでもほんの少量しか出ていない・・・という場合も危険な場合があります。
様子を見ないですぐに動物病院を受診しましょう。
大抵の場合は、元気や食欲がなくなる・触ると痛がって怒る・吐くなど何かしらサインが出てきますが、中には詰まっているのに元気食欲はある場合もありますので、オス猫でおしっこが頻回の場合は元気食欲があっても様子を見ない方が賢明です。
(ある程度状態が進めば元気食欲もなくなっていきますが、処置は早い方が回復も早いです)
もし詰まっていたらどうするのか?
鎮静をかけて尿道カテーテルを入れ、おしっこを出す処置と膀胱を洗う処置をします。
合わせて血液検査をおこない、腎臓へのダメージがあるかを確認します。
また尿検査をおこない、原因を調べます。
基本的には入院、状態によって入院日数は異なります。
※これは当院の場合ですので、病院によってはやり方が違うこともありますのでご了承下さい。
わんちゃんでもおしっこの病気はもちろんあります。
そしてわんちゃんの場合は、結晶が結石になっている子もちょくちょくいます。
これは特にメス犬の場合が多いです。
今月は膀胱結石の手術をしたわんちゃんもいました。
これがその時の結石の写真です。
定規のあてかたが悪いのでわかりにくいですが、2.5センチほどの大きさがありました。
この石が膀胱にあって中を傷つけてしまい、出血がひどかったです。
結石がある=即手術ではないのですが、内科療法をおこなっても改善がない・石が大きいもしくは数が多い・石が尿道に詰まってしまったなどの場合は手術が必要となります。
わんちゃんの場合、体質的に結石ができやすい犬種があります。
シュナウザー、シーズー、ダルメシアン、コーギー、ペキニーズ、パグ、ダックス、ヨーキーなどです。
猫ちゃんもわんちゃんも、結晶や石が出来る原因はいくつかあります。
・体質
・食餌内容
・細菌感染
・肥満
・ストレス
これらの中で予防ができることは食餌(と肥満)です。
ミネラル分や塩分の多い食餌やオヤツは控える(鰹節や煮干しは動物用であっても好ましくありません)、体重が増えないよう気を付けるというのは飼い主さんが出来る大切な予防です。
特に猫の場合は、体質が強い子だと繰り返しおしっこの病気になってしまうことがありますので、一度膀胱炎になったら食餌の見直しが大切です。
寒い時期は膀胱炎をおこしやすいといわれます。
くれぐれもおしっこの状態がおかしくないか注意してみてあげて下さいね。
ミネラル分や塩分の多い食餌やオヤツは控える(鰹節や煮干しは動物用であっても好ましくありません)、体重が増えないよう気を付けるというのは飼い主さんが出来る大切な予防です。
特に猫の場合は、体質が強い子だと繰り返しおしっこの病気になってしまうことがありますので、一度膀胱炎になったら食餌の見直しが大切です。
寒い時期は膀胱炎をおこしやすいといわれます。
くれぐれもおしっこの状態がおかしくないか注意してみてあげて下さいね。
2015年10月29日
猫の風邪
今月は猫ちゃんの風邪症状で来院される方がとても多いです。
例年より明らかに多く、地域もバラバラですので、今年は全体的に多いのだと思います。
・成猫
・症状が重い(食欲がまったくなくなる)
・ワクチン未接種(過去に接種したことはあるがその後何年もあいている含む)
・多頭飼い
これらの条件が重なっているおうちが多く、自宅内で感染が広がってしまっています。
猫ちゃんの風邪症状とは…
・くしゃみ
・鼻水
・目ヤニ
・涙目
・鼻がきかなくなり食欲がなくなる
これらはすべて出るわけではありません。
涙目だけでも風邪の場合がありますので、注意が必要です。
風邪のウィルスもいくつかあり、厄介なのがカリシウィルスです。
これは上記の症状のほかに、口内炎や舌潰瘍ができるので、口が痛くなって余計に食欲がなくなります。
口が痛いのでよだれが多く出ることもあります。
猫ちゃんは食欲がない状態が続くと、肝臓に影響が出て命にかかわる場合があります。
少しづつでも食べていればまだいいのですが、まったく食欲がなくなった場合はすぐに受診しましょう。
重症化すると週に何度も通院が必要になってしまいます。
![]()

一度良くなっても、季節の変わり目や抵抗力が落ちるとまた症状が出ることが多いです。
定期的なワクチン接種がとても大切です。
特に2匹以上の多頭飼いのおうちでは感染が広がると特に大変ですから、必ず接種しておきましょう。
外にでない完全室内飼いの猫ちゃんでも飼い主さんが靴につけて運んでしまったり、網戸越しに感染する例もあります。
実際、現在来院されている方の半分近くは完全室内飼いのおうちです。
外にでないから大丈夫!ではないので、注意して下さいね。

例年より明らかに多く、地域もバラバラですので、今年は全体的に多いのだと思います。
・成猫
・症状が重い(食欲がまったくなくなる)
・ワクチン未接種(過去に接種したことはあるがその後何年もあいている含む)
・多頭飼い
これらの条件が重なっているおうちが多く、自宅内で感染が広がってしまっています。
猫ちゃんの風邪症状とは…
・くしゃみ
・鼻水
・目ヤニ
・涙目
・鼻がきかなくなり食欲がなくなる
これらはすべて出るわけではありません。
涙目だけでも風邪の場合がありますので、注意が必要です。
風邪のウィルスもいくつかあり、厄介なのがカリシウィルスです。
これは上記の症状のほかに、口内炎や舌潰瘍ができるので、口が痛くなって余計に食欲がなくなります。
口が痛いのでよだれが多く出ることもあります。
猫ちゃんは食欲がない状態が続くと、肝臓に影響が出て命にかかわる場合があります。
少しづつでも食べていればまだいいのですが、まったく食欲がなくなった場合はすぐに受診しましょう。
重症化すると週に何度も通院が必要になってしまいます。

一度良くなっても、季節の変わり目や抵抗力が落ちるとまた症状が出ることが多いです。
定期的なワクチン接種がとても大切です。
特に2匹以上の多頭飼いのおうちでは感染が広がると特に大変ですから、必ず接種しておきましょう。
外にでない完全室内飼いの猫ちゃんでも飼い主さんが靴につけて運んでしまったり、網戸越しに感染する例もあります。
実際、現在来院されている方の半分近くは完全室内飼いのおうちです。
外にでないから大丈夫!ではないので、注意して下さいね。

2015年10月22日
漢方薬による脱毛の改善例
当院で取り扱っております、イスクラ産業㈱の漢方サプリメントQUANPOW(クアンポー)シリーズ。
症例のご紹介をします。
今回使用しているのは007潤華です。
毛並みの養生に使用し、脱毛の改善にも役立ちます。今回の使用目的とは異なりますが、目にも良い漢方です。
原材料は沙苑子、黄精、枸杞子、鶏血藤、桑の実、三棱、莪朮、朝鮮人参など。
1例目 トイプードル 耳の毛の脱毛
症例のご紹介をします。
今回使用しているのは007潤華です。
毛並みの養生に使用し、脱毛の改善にも役立ちます。今回の使用目的とは異なりますが、目にも良い漢方です。
原材料は沙苑子、黄精、枸杞子、鶏血藤、桑の実、三棱、莪朮、朝鮮人参など。
いずれも経過が長い症例で、薬用シャンプー療法をおこなっていましたが、シャンプーのみではかゆみは抑えられても脱毛の改善まで至らず、漢方を始めたところ症状が明らかに変化しました。
※投薬については潤華のみです。今回ご紹介する子たちはその他の内服薬は使用しておりません。
1例目 トイプードル 耳の毛の脱毛
投薬前

投薬開始から4カ月後

投薬開始から半年経過

まだ毛の薄い部分はありますが、赤い部分はありません。
![]()
2例目 MIX犬 背中の脱毛
投薬前

投薬1カ月後(写真の向きが1枚目と反対です)

毛も生えてきて赤みがひきました。
3例目





投薬開始から4カ月後
投薬開始から半年経過
まだ毛の薄い部分はありますが、赤い部分はありません。
2例目 MIX犬 背中の脱毛
投薬前
投薬1カ月後(写真の向きが1枚目と反対です)
毛も生えてきて赤みがひきました。
3例目
ミニチュアダックス 耳の赤み、脱毛、フケ
投薬前
投薬2カ月後

フケがおさまり、赤みもひきました。脱毛部分も縮小しています。
フケがおさまり、赤みもひきました。脱毛部分も縮小しています。
4例目
MIX犬 あごの下の脱毛、かゆみ
投薬前
投薬2週間後(写真横向きになっています)
細かい毛が生え始めています。
投薬1カ月後
毛が生えました。
投薬2カ月後
黒くなっていた部分は皮膚がかたかったのですが、黒ずみも取れてやわらかくなりました。
改善には個体差があり、すぐに症状が緩和した子もいれば、数カ月かかった子もいます。
また似たような症例でも皮膚病の原因はさまざまですので、すべての症例に効果があるわけではありません。
まずは2週間、最低でも1カ月は続けていただくことが大切です。
漢方のご相談は当院まで!
ますだ動物クリニック ☎0547-33-6010
(お問合せは獣医師への確認が必要であることが多いため、診察時間内にお願いします)
2014年11月05日
マンソン裂頭条虫
まんそんれっとうじょうちゅうと読みます。
マンソン裂頭条虫とは、動物のお腹に寄生する虫です。
これが寄生する原因はこの虫を持っているカエルやヘビを食べることです。
この辺りは田んぼが多いので、カエルを食べてしまう猫ちゃんがいて珍しい寄生虫ではないのですが、都会では滅多に見ないそうです。
うんちに白い虫が出た!と言われた場合、条虫かマンソンの可能性が高いのですが、違いは太さです。
条虫の方が素麺だとすると、マンソンはきしめんです。
マンソンの方が太いんです。
うんちから出ることもありますし、吐いたものに虫が出ることもあります。
このマンソンさんは途中で切れて出てくることが多いのですが、長いきれいな状態で出てきたものがありました。
院長が専門学校で動物看護について教えている生徒さん達に見せたいということで、飼い主さんに許可をいただいて標本にしました。
以下その写真を載せますが、こういった虫が苦手な方はご注意下さい。
そして、いつものようにこのまま写真を載せますとeしずおかのトップページに出てしまうため、まずは関係ない写真です。

↑ 玄米(白い方)が若干はみ出ていますが、気にしないで下さい・・・
よく大きい猫ですね!と驚かれますが、飼い主としては白が膨張色で大きく見えるだけと思っています。あとは隣にいる比較対象の三毛猫が小さいせいです。
体重も5㎏ないんですよ。猫ちゃんは6㎏こえるとかなり大きいです。
話がそれました。では、本題です。
これがマンソン裂頭条虫です!

きしめんっぽいのがわかるでしょうか?
それともうどん位と思われたでしょうか。
きしめんも太さが違ったりするので、このあたりは個人の主観にお任せします。
こんなに長いのがお腹にいると思うと気持ち悪いですよね・・・
成猫の場合は下痢など特に症状を示さないこともありますが、お腹にいていいものでもありません。
マンソンの場合、駆除方法が注射しかありません。しかもこの注射高いです。
予防は猫を外に出さないことです。
マンソン裂頭条虫とは、動物のお腹に寄生する虫です。
これが寄生する原因はこの虫を持っているカエルやヘビを食べることです。
この辺りは田んぼが多いので、カエルを食べてしまう猫ちゃんがいて珍しい寄生虫ではないのですが、都会では滅多に見ないそうです。
うんちに白い虫が出た!と言われた場合、条虫かマンソンの可能性が高いのですが、違いは太さです。
条虫の方が素麺だとすると、マンソンはきしめんです。
マンソンの方が太いんです。
うんちから出ることもありますし、吐いたものに虫が出ることもあります。
このマンソンさんは途中で切れて出てくることが多いのですが、長いきれいな状態で出てきたものがありました。
院長が専門学校で動物看護について教えている生徒さん達に見せたいということで、飼い主さんに許可をいただいて標本にしました。
以下その写真を載せますが、こういった虫が苦手な方はご注意下さい。
そして、いつものようにこのまま写真を載せますとeしずおかのトップページに出てしまうため、まずは関係ない写真です。
↑ 玄米(白い方)が若干はみ出ていますが、気にしないで下さい・・・
よく大きい猫ですね!と驚かれますが、飼い主としては白が膨張色で大きく見えるだけと思っています。あとは隣にいる比較対象の三毛猫が小さいせいです。
体重も5㎏ないんですよ。猫ちゃんは6㎏こえるとかなり大きいです。
話がそれました。では、本題です。
これがマンソン裂頭条虫です!
きしめんっぽいのがわかるでしょうか?
それともうどん位と思われたでしょうか。
きしめんも太さが違ったりするので、このあたりは個人の主観にお任せします。
こんなに長いのがお腹にいると思うと気持ち悪いですよね・・・
成猫の場合は下痢など特に症状を示さないこともありますが、お腹にいていいものでもありません。
マンソンの場合、駆除方法が注射しかありません。しかもこの注射高いです。
予防は猫を外に出さないことです。
2013年08月31日
うさぎさんの歯
うさぎさんは一生歯が伸び続ける動物です。
固いものをかじったり、チモシーなどの牧草を食べることで、伸びすぎるのを防いでいます。
しかし、それらをあまりしないと歯が伸び過ぎてしまい、かみ合わせもおかしくなります。

上の前歯が伸びて曲がってしまっているのがわかりますね。
こうなってしまうと、切るしかありません。
前歯だけであればよほど暴れるうさぎさんでなければ、鎮静なしで処置します。
奥歯も大人しい子は処置出来ますが、中には鎮静をかけないと出来ない場合もあります。
また一度なると繰り返すことが多いです。
1~2ヶ月ごとに定期的に切りに来院される方もいます。
前歯は見えるのでわかりやすいですが、奥歯は確認するのは難しいです。
奥歯は伸びてくるとほっぺの内側にあたって炎症を起こすこともあります。
こうなるとうさぎさんは食欲が落ちたり元気がなくなりますので、飼い主さんも気付かれると思います。
最近食欲が落ちてきた、うんちが小さくなったなどの症状がみられましたら、動物病院を受診しましょう。
症状がなくても、伸びているかどうか定期検診を受ける方もいらっしゃいますので、お気軽にご来院下さいね。
固いものをかじったり、チモシーなどの牧草を食べることで、伸びすぎるのを防いでいます。
しかし、それらをあまりしないと歯が伸び過ぎてしまい、かみ合わせもおかしくなります。
上の前歯が伸びて曲がってしまっているのがわかりますね。
こうなってしまうと、切るしかありません。
前歯だけであればよほど暴れるうさぎさんでなければ、鎮静なしで処置します。
奥歯も大人しい子は処置出来ますが、中には鎮静をかけないと出来ない場合もあります。
また一度なると繰り返すことが多いです。
1~2ヶ月ごとに定期的に切りに来院される方もいます。
前歯は見えるのでわかりやすいですが、奥歯は確認するのは難しいです。
奥歯は伸びてくるとほっぺの内側にあたって炎症を起こすこともあります。
こうなるとうさぎさんは食欲が落ちたり元気がなくなりますので、飼い主さんも気付かれると思います。
最近食欲が落ちてきた、うんちが小さくなったなどの症状がみられましたら、動物病院を受診しましょう。
症状がなくても、伸びているかどうか定期検診を受ける方もいらっしゃいますので、お気軽にご来院下さいね。

